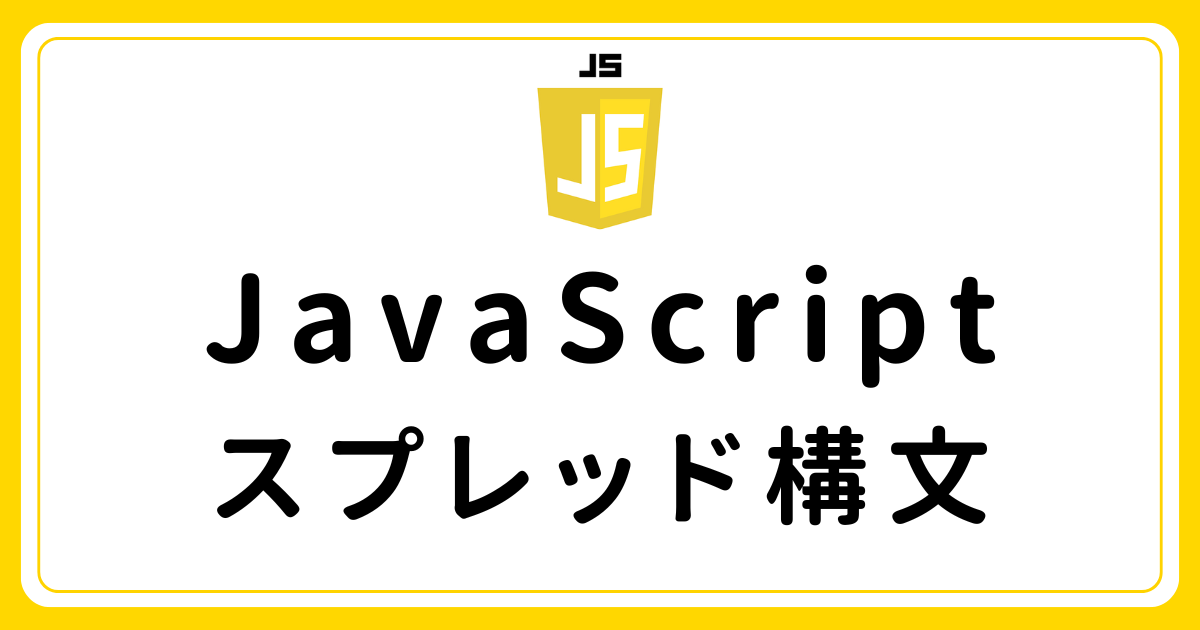目次
1. 本記事のポイント
- JavaScriptのスプレッド構文(
...)と残余引数(rest parameter)の基本構文を整理 - 配列・オブジェクト操作、関数定義での具体的な活用シーンを紹介
- 実務でありがちな誤用や混同ポイントを解説
2. スプレッド構文と残余引数とは?
JavaScriptでは、...(ドット3つ)を使った構文が2種類存在します。1つはスプレッド構文(spread syntax)、もう1つは**残余引数(rest parameter)**です。
スプレッド構文は、配列やオブジェクトを展開して要素を取り出す際に使われます。代表的な用途は、配列のコピー、結合、関数呼び出し時の引数展開です。
一方、残余引数は関数定義で使われ、可変長の引数を1つの配列として受け取る手段です。どちらも構文上は ... を使いますが、使用位置と目的が異なります。
スプレッド構文と残余引数はどちらもES6以降で導入されており、可読性と柔軟性を高めるために広く使われています。実務では、APIレスポンスの加工やパラメータのバインド、ReactのProps展開など多くの場面で利用されます。
3. 詳細解説
配列のコピー・結合(スプレッド構文)
配列を浅くコピーしたり、複数の配列を結合する場面で使います。
JavaScript
const original = [1, 2, 3];
const copy = [...original]; // 浅いコピー
const extended = [...original, 4, 5]; // 要素の追加
console.log(copy); // [1, 2, 3]
console.log(extended); // [1, 2, 3, 4, 5]
関数引数への展開(スプレッド構文)
引数の配列を展開して関数に渡したい場合に使用します。
JavaScript
function sum(a, b, c) {
return a + b + c;
}
const nums = [10, 20, 30];
console.log(sum(...nums)); // 60
関数の残余引数の取得(rest parameter)
可変長の引数を受け取る関数で、引数を1つの配列として受け取れます。
JavaScript
function logAll(first, ...others) {
console.log("first:", first);
console.log("others:", others);
}
logAll("a", "b", "c", "d");
// first: a
// others: ["b", "c", "d"]
オブジェクトのコピー・マージ(スプレッド構文)
オブジェクトでも同様に浅いコピーやプロパティの上書きマージに使えます。
JavaScript
const obj1 = { x: 1, y: 2 };
const obj2 = { y: 99, z: 3 };
const merged = { ...obj1, ...obj2 }; // yが上書きされる
console.log(merged); // { x: 1, y: 99, z: 3 }
4. よくあるミス・誤解・落とし穴
...の前後関係を見誤ると、スプレッドと残余引数を混同しやすくなります。スプレッドは展開、残余引数は集約という機能の違いに注意が必要です。- 配列・オブジェクトのスプレッドは浅いコピーであるため、ネストされた構造では意図しない共有が発生する可能性があります。
- 関数定義の引数順に注意が必要です。残余引数は最後の引数にしか使えません。
- オブジェクトのスプレッドでは、順序が後のものが前を上書きするため、マージの優先順位を意識しないと意図しない値の上書きが起きます。
5. まとめ
スプレッド構文と残余引数は、どちらも ... を使いますが、意味と用途はまったく異なります。配列やオブジェクトの展開・複製・結合にはスプレッド構文を、関数での可変長引数の受け取りには残余引数を使います。
構文の柔軟さゆえに誤用しやすいため、「展開か集約か」を軸に目的に応じて正しく使い分けることが重要です。